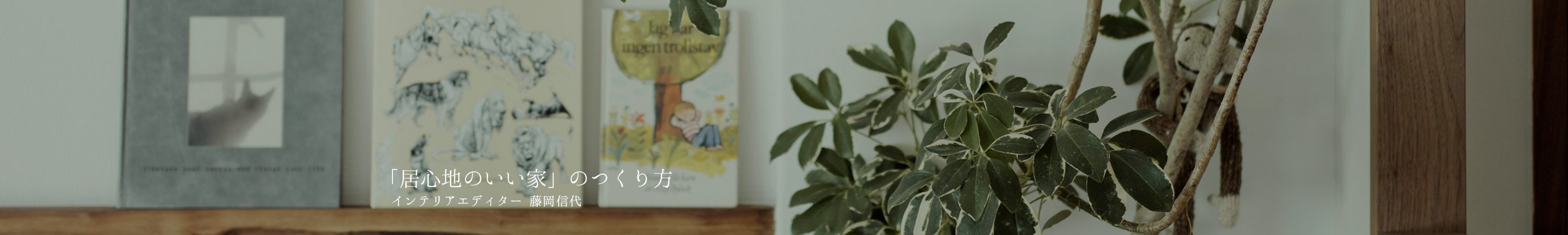
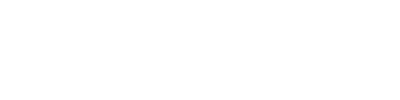
 K邸(芦屋市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
K邸(芦屋市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
前回からは、インテリアを楽しむ家づくりのお話をしています。
今回のテーマは、“照明”。
いわゆる照明器具は、持ち家・賃貸に関わりなく、好きなデザインを楽しむことができますが、“光をデザインする”ことは、家づくりの段階からプランができていたほうがベターです。
光をデザインする?
そう、光はデザインできるのです。
 A邸(寝屋川市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
A邸(寝屋川市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
そのことを知ったのも、前職『PLUS1 LIVING』での取材からです(編集部注:藤岡さんは主婦の友社『PLUS1 LIVING』の元編集長)。照明器具は、ほんとうに素敵なデザインのものがたくさんあり、日本でも輸入の照明器具がいろいろ選べるようになりました。お手頃なところでは、IKEAでも北欧デザインの照明器具が手に入りますよね。照明器具をどうやって選び、コーディネートすればいいのかな?と思って、さまざまなプロの方に取材にいきました。そして、そこで深く感銘を受けたのは、“光をデザインする”ということだったのです。
光は、人間の心理にとても大きな影響を与えます。
昼間の明るくてやや白い太陽光は活動を促し、夕方のやや暗くてオレンジ色の太陽の光はリラックス効果がある、という話は、見聞きされたことがあるのではないでしょうか?オフィスの照明が、昼間の太陽光のように白く明るい蛍光灯なのは、活発に働き、能率を上げるためなんですね。ということは、寝室の照明が明るい蛍光灯では、リラックスして眠りにつくことができにくい。寝室の灯りは、暗めの、オレンジっぽい光のほうがいい、ということになります。
ほかにも視線を誘導する効果があるので、動きを促したり、ショーアップの演出をしたりなどなど、光のデザインでできることはたくさんあります。いろいろな効果やテクニックを知っていると、身体感覚にもしっくりときて、素敵なインテリアを創ることができるのです。
とはいうものの、実際に光をデザインするのは、プロの手を借りたほうがいいかもしれません。
これも自宅をリフォームしたときのこと、多少の知識を持っていた私は、自宅で実践してみようと、いくつか“光のデザイン”に挑戦してみました。結果は、思いどおりにいったことも、いまいちだったことも両方ありました。
まずは、思いどおりにいったこと。
それは、寝室の照明器具をダウンライトのウォールウォッシャーにしたことです。天井埋め込みにできるダウンライトは、照明器具が目立たず、もっともシンプルに仕上げられる照明だと思います。複数のダウンライトをうまく配置すれば、部屋全体を明るくすることも可能。ですが、このダウンライト、ものすごく配置が重要なのです。
私が試してみたいと思ったのは、ダウンライトを部屋の壁に近いところに配置し、まっすぐ床に落ちる光だけでなく、壁を照らす光の反射も利用する手法です。これをウォールウォッシャーと言います。
壁に反射する光は、いわゆる“間接照明”と呼ばれる照明になります。光が壁にあたって分散することで、やわらかい光になるのですね。反射(バウンス)させるので、“バウンス光”とも言います。日本人に比べて、光の感受性が強い(つまり強い光をまぶしく感じる)と言われる西欧人に好まれます。
また、人間の目は通常の姿勢では水平に視線がいくので、天井から垂直に降りてくる光は感じにくく、壁などにあたっている光は目につきやすい、ということもあります。ダウンライトが照らすのは、通常、床面になるので、もっとも明るく見えるのは床面。それに対して、壁に当たっている光は壁面を明るく見せますので、“明るさが見えやすい”のですね。実際の明るさ以上に、明るく感じるのです。
そんな知識を詰め込んだ(笑)私は、「ダウンライトにするなら、壁面にも光を充てなくちゃね!」と意気込んでいました。そして、リフォームの際にそのように指示したつもりだったのですが…。
 O邸(尼崎市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
O邸(尼崎市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
ここからは、失敗談です。
リフォーム用の図面には、照明デザイン専用の図面はありませんでした。私の指示は、ダウンライトを4灯つける、というだけのもの。肝心の配置については、意図が伝わっていなかったのです。というか、「伝わるもの」と勝手に思い込んでいました(笑)、工務店さんはプロなわけだし。
伝わってなかった!と気づいたのは、工事の途中の様子を見にお邪魔したときでした。リフォーム中に何度か様子を見に行かせてもらったのですが(もちろん現場監督さんにお伺いを立てた上で)、まさに電気工事の方がダウンライトを取り付けようというところだったのです。ふと天井を見上げると、天井の中央と部屋の四隅の、それぞれ中間地点あたりにダウンライト用の穴が開けられようとしていました。
「あ、そこじゃないです!」と思わず叫びました。「もっと部屋の隅の方に寄せて。光が壁に当たるようにしてほしいのです」。
工務店の棟梁と電気工事の方は顔を見合わせて、怪訝な顔をしています。私は一生懸命、どんな光にしたいのかを説明しました。じっと耳を傾けていた電気工事の方は、そこで一言、「ウォールウォッシャーにしたいのね」。
さすがプロです。意図するところを伝えれば、一発で伝わりました。そこで、空けてしまった穴はふさぎ、あらためて4つのダウンライトの位置を、確認しながら決めてくれました。
このときはたまたま現場に居合わせることができたので、その場で修正がききましたが、本来、新築もリフォームも、工事は図面の指示に従うのが原則です。つまり、図面にない指示は受けてもらえません。意図していることをしっかり図面にしておくこと。これは素人には難しいですから、やはりいかに設計担当者に意図を伝えておくか、コミュニケーションを密にしておくか、とういことが大事なのです。
いまいちだったこと。これは細かいことを揚げればキリがありません(笑)。でも、一言で集約すれば、「明るさの加減を見極めることができなかった」ということになると思います。照明器具の位置が近すぎて、必要以上に明るくなってしまった。あるいは、もう少し明るさが必要だったのに照明器具のワット数が足りなかった…などなど。
このあたりは、素人には見極めが難しいところですね。幸い、多すぎた照明器具は、「つけないようにする」という選択肢があるので、日常生活には問題ないですが。
 H邸(堺市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
H邸(堺市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
光のデザインは、心理面に大きな影響を与える。
ということは、「その部屋でどんな時間を過ごしたいか?」をあらかじめイメージして、それに合う光をデザインしなければならないということです。けれども、私の失敗体験からわかるように、明るさ一つとっても、「実際につけてみないと、わからない」ということはたくさんあります。
最近は、欧米式のちょっと暗めの照明も好まれるようになってきて、あえて暗めにするケースもふえていますね。リラックス空間ではすごくいいことだと思います。けれども、老眼が進んでくると、暗い空間というのは、ちょっとしたことをするにも「見えない」というストレスが出てくるのです。これは年齢を重ねてみなければわからないことでした(笑)。
これらの問題を解決するには、一つには、「光のデザインを決め込まない。あとで変えられるようにする」ということになると思います。これまでも、同じようなことを書いてきましたが、「ライフスタイルに変化はあるもの」と織り込んでおいて、あとでどうとでもなるように、ゆるい部分をつくっておくのです。
具体的には、ベースになる全体照明はほどよい明るさにしておいて、光を足す調整を後づけの照明器具でするようにします。照明器具用に、コンセントを多めに配置しておくとよいと思います。
テーブルランプやフロアランプ、スポットライト、ペンダントライトなど、インテリアの演出としても使える照明器具は、いろいろとあります。ベースの照明でしっかり光を作りこんでしまうと、これらの照明器具を足したとき明るくなりすぎてしまう可能性があるので、やはりベースの明るさはほどほどに。照明器具の光は、ほの暗い空間に灯っているからこそ美しいし、ドラマティックに感じるのです。
 K邸(芦屋市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
K邸(芦屋市)/設計施工:フクダ・ロングライフデザイン
試しに一度、部屋の全体照明を消して、お手持ちの照明器具を、いろいろな場所にスポット的に置いてみてください。部屋の印象が変わったり、見えてくる景色が違うはずです。照明器具は、オブジェとして形のデザインを楽しむこともありますが、やはりこの光の効果をデザインとして楽しめる点が魅力。ぜひ、光のデザインも楽しんでみてほしい、と思います。
これはあくまで私の印象ですが、家づくりのときに、収納や家具や照明をなんでもいっぺんに「造りつけ」にしてしまうケースがあるように感じます(むしろ、そのほうがおしゃれ、と考えている人もいるような…?)。
それは本当にもったいない。家具も照明器具も、たくさんのデザイン、バリエーションがあるのですから、ぜひいろいろと楽しんでほしい。家に造りつけてしまうと、その楽しみはなくなってしまいますから、ぜひ長い時間をかけてインテリアをつくっていく楽しみをとっておいてほしいと思います。
そう考えると、ベースとなる建物に必要なことは、「いろいろな変化を受け止められる」ということに尽きるのかもしれません。
Chat with the Curator
2016.5.2
「光をデザインする」大事なポイントだと思いました。照明器具のデザインは写真や実物を見て選ぶことができますが、「光」は違いますもんね。 インテリアで1番見落としてしまいそうなところだと感じました。でも、長所はコンセントを多めに配置しておけばあとから光をデザインすることができるので、そこは先に織り込んでおくポイントですね。 現場の図面が全て!という点で私の失敗談もいいですか?(笑)玄関から入ってすぐにある部屋の扉を壁に変えて塞ぎました。その部屋のスイッチはその扉の横に付いています。入口が変わったのに部屋の電気のスイッチはそのままでした。部屋に入ってから真っ暗闇の中スイッチまで辿りつかないと灯りは点らない。指示をちゃんと出さなかった私の痛恨のミスでした。

2016.5.9
2016.5.16
インテリアの中で「光をデザインする」は感覚的な要素が大きいですね。以前、よく行ってたインテリアショップがデパートのテナントに入って、ものスゴク楽しみで行ってみると全然違うお店に感じました。なんなんだろう?この違和感は!!
少し引いて辺りを見渡して見るとわかりました。照明でした!!デパートのあの照明の明るさが、路面店のイイ雰囲気を根こそぎ奪っていました。笑!
普段からいろんな場所で少し意識することで、自分の好きな明るさや苦手な明るさも見つけるコトができそうですね。
「暮らしの経験値」を意識してココを上げていきたいな~って思いました。

2016.5.23
1
7月26日公開
ハウジング誌『PLUS1 LIVING』の元編集長が考える「居心地のいい家」。機能性を重視されがちな新築マンションで、軽やかに「いい按配」のリフォームを施す秘訣とは?
2
10月13日公開
自分の住まいを持つとき、様々な条件や制約のなかで、計画的に「満足度」を考える。藤岡さんの実体験に学ぶ、欠点も愛着に変える住まいとのクールな付き合い方。
3
11月10日公開
あえて完成させない家づくり。建物ができたら、そこからDIYで楽しみながら手入れしていく。そんな欧米では当たり前の考え方を参考に「家の完成」について考えます。
6
2月23日公開
味わいがあるけど手入れが大変そうな自然素材。性能や費用だけでなく「衛生観念」を基準に無垢材と新建材を使い分けてみると、無理なく住まいの経年変化と付き合えるでしょう。
7
3月22日公開
インテリアを楽しむ秘訣は実は「壁」にありました。家具が引き立つ「壁」の使い方、そして発想の転換で配置する「窓」。インテリアのための目からウロコのプランのポイントをご紹介。
8
4月26日公開
照明器具選びは光そのものをデザインすることでもあります。思い描いた光の雰囲気を正しく伝えるためには、照明の知識は然ることながら、工務店との綿密なコミュニケーションが必要です。
9
5月31日公開
自分の好みを周りの人に正しく説明できますか?空間の「好き」をビジュアル化したり言語化したりすることで、家づくりに携わる人たちにより明確なイメージを伝えられるようになります。
10
6月29日公開
かっこいい家、おしゃれな家、と思わせるために必要な鍵はやはりインテリアにありました。印象的な「見せ場=フォーカルポイント」を作ることで空間がぐっと引き締まります。
11
7月26日公開
もう一度、家を建てるとしたら…。いまの暮らしの中で感じる不便さや不自由さこそが理想の家づくりのヒントになります。愉しい家にするために必要なふたつのポイントをもう一度おさらいしましょう。
12
8月30日公開
連載最終回。「本当にいい家」とは何か?全12回のコラムを通じて藤岡さんが考察してきた理想の家づくりについて、フクダ・ロングライフデザインの福田社長にインタビューしました。